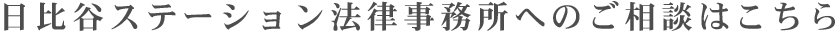
※ *がついた手続きは前後することもあれば、繰り返し行われることもあります。
「租税訴訟」という手続きは法律上ありませんが、一般的に、租税に関する訴訟を指して租税訴訟と呼びます。税務訴訟と呼ぶこともあります。
租税に関する訴訟は、行政事件訴訟や民事訴訟等があります。課税処分を争う訴訟の大部分は行政事件訴訟です。
租税訴訟・税務訴訟には以下の8つの類型があります。
租税訴訟の大部分を占める訴訟類型です。取消訴訟とは、処分が違法であることを理由として、その取り消しを求める訴訟です。
無効確認訴訟とは、処分に無効原因となる違法性があることを理由として、処分が存在しないこと又は処分の効力が無いことの確認を求める訴訟です。取消訴訟とは異なり、出訴期間の制限を受けませんし、不服申立前置主義の適用もありません。
しかし、「無効」というためには、極めて高いハードルを越える必要があります。実際のところは、出訴期間を経過した取消訴訟の救済ルートといわれることがあります。
争点訴訟とは、私法上の請求をする民事訴訟ですが、行政処分が無効であることを理由とするものです。例えば、滞納処分が無効であることを理由として、公売財産の買受人に対して公売財産の返還を求める訴訟です。
行政庁が処分をしないことの違法の確認を求める訴訟です。例えば、税務署長が納税猶予申請に対して何も処分をしない場合に、不作為の違法確認を求めます。
行政庁に処分または裁決をする旨を命じることを求める訴訟です。不作為の違法確認訴訟よりも直裁的な訴訟といえます。
行政庁が処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟です。
過誤納金の還付を求める訴訟です。ただし、まずは、租税確定処分の取消を求める必要があります。
租税職員の違法な公権力の行使によって受けた損害賠償を国または地方団体に求める訴訟です。特別な訴訟類型のように思えますが、訴訟手続法上は純粋な民事訴訟です。
国家賠償を求めるためには原則として公務員の故意または過失が要件となります。
また、審査請求や取消訴訟の手続きを経ることなく、国家賠償の請求をできることもあります。例えば、固定資産の価格や固定資産税の税額を過大に決定したケースなどがあります。
課税処分の取消訴訟を提起するためには、訴訟要件を充たす必要があります。特に注意が必要な訴訟要件は、不服申立前置と出訴期間になります。
不服申立前置主義とは、不服申立手続きを経なければ出訴できないというルールのことです。異議申立や審査請求ができる処分に対しては、異議申立や審査請求をする必要があります。たとえば、税務署長の処分に対しては、原則として、審査請求と異議申立の両方の手続きを経る必要があります。
不服申立前置主義がルールとなっている理由は次の二つです。
なお、都道府県民税賦課決定処分と市町村民税賦課決定処分は、1通の納税通知書で合わせて行われることがあります。1通の通知書のため、同じ処分であると誤解するかもしれませんが、それぞれ別個の処分になります。そのため、それぞれ別々に不服申立手続きを経る必要があります。
不服申立が不適法で、却下された場合には、不服申立手続きを経たことにはなりません。
適法な不服申立が誤って却下された場合には、不服申立前置の要件をみたします。
不服申立前置主義の例外として、決定または裁決を経る必要がない場合があります。次の4つの類型があります。
取消訴訟は、処分または裁決のあったことを知った日から6ヶ月以内に提起する必要があります。また、処分または裁決のあった日から1年を経過する前に取消訴訟を提起する必要があります。
ただし、正当な理由があるときは別です。例えば、出訴期間中に阪神淡路大震災が起き、その影響を受けた場合には、正当な理由があるとされました。
なお、審査請求をする場合には、出訴期間は、審査請求に対する裁決を知った日から6ヶ月となります。